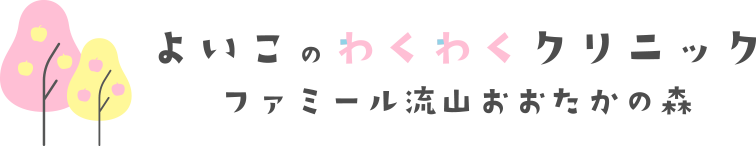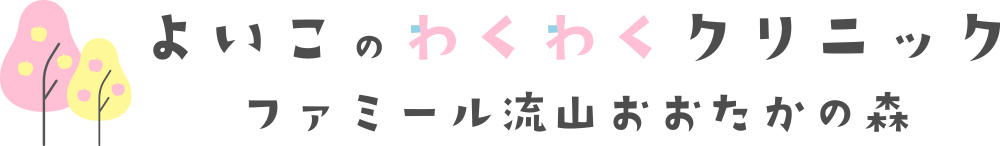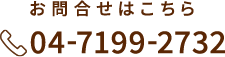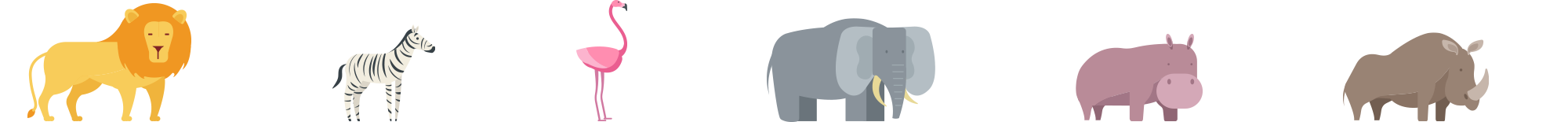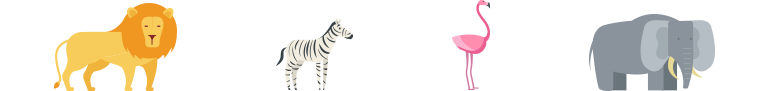🍎目薬はどうやってさしたらいいの?
子どもの目やに、目のかゆみ、充血などは
小児科でもご相談の多い症状です。
目薬をもらったけど、子どもにさしたことがない、嫌がる子にどうやってさせばいいの?と困ったこともあるかと思います。今回は小児科で多い症状と目薬の使い方についてお話します。
子どもの目やにはどうして出るの?
目やには目の表面の古い細胞や分泌物、ゴミなどが涙で洗い流されることによって作られます。小さな子どもは新陳代謝が活発で、目と鼻をつなぐ通り道(鼻涙管)も狭いため、生理的に目やにが出やすいです。赤みやかゆみ、痛みなどがなければ、清潔にしてしばらく様子をみても構いませんが、症状が続くようなら一度受診してみましょう。
受診した方がよい目の症状
治療が必要なのは、風邪やアレルギーなどが原因で目やにが出たり、目のかゆみや充血がある場合です。多量の鼻水や鼻の粘膜の腫れにより、目と鼻をつなぐ通り道が通過障害をおこしてしまうと、目で作られた涙が鼻の方へ流れず溜まってしまい、それが乾燥して目やにとなります。
涙が溜まったところに細菌が繁殖すると、目やにはべっとり・ネバネバとした黄色~緑色になり、目が充血したり、痛みやかゆみが出たりすることもあります。このような細菌性結膜炎は、抗菌薬入りの目薬を使って治療します。
流行性角結膜炎、いわゆる“はやり目”は、アデノウイルスが原因のウイルス性結膜炎です。発熱や喉の痛みを伴うときは咽頭結膜熱(プール熱)と呼ばれます。いずれの場合も、目の充血や目やに、目の腫れなどの症状を伴います。特効薬はありませんが、症状を和らげるために抗菌薬やステロイドの入った目薬が処方される場合もあります。
アレルギー性結膜炎は、花粉やハウスダスト、ダニなどのアレルゲンが白目の表面(結膜)に付くことで、目のかゆみや充血、涙目などの症状を引き起こします。子どもはかゆみを我慢できずに強く目をこすりすぎてしまうので、目が腫れたり、白目の部分がゼリー状に浮腫んだりすることもあります。
治療には、アレルギーを抑える飲み薬と点眼薬が有効です。花粉症では、花粉の飛散時期の数週間前から目薬をしておくと、症状を軽く抑えられるとされています。毎年決まった季節に症状が出るお子さまは、かゆみが出る前に予防的に目薬を使ってあげるとよいでしょう。
目やにの取り方
目やにの中には細菌やウイルスがいる場合があります。こまめに拭き取り、目を清潔に保ちましょう。目薬を使うときも、目やにを取り除いてからさすようにしましょう。
清潔なガーゼなどを濡らして、目頭を軽くおさえて目やにを取り除きます。使い捨ての清浄綿なども便利です。無理に取ろうとせず、ガーゼの面を変えながら少しずつ取ってあげましょう。片目だけ目やにがひどい場合は、もう片方に感染しないように、症状の軽い方の目から拭き、同じガーゼを使わないように気を付けてください。
目薬のさし方
お子さまを膝の上に仰向けに寝かせます。動いてしまう場合は大人の両膝で頭を挟んで固定します。下まぶたをそっと引っ張り、目薬を1滴落とします。目薬は1滴で十分な濃度に調整されているので、何滴もささないようにしましょう。点眼後は目頭を軽く押さえ、数十秒目を閉じたままにしておくと効果的です。
下まぶたを引っ張るのを嫌がる場合は、仰向けに寝かせ、目をつぶったまま目頭に1滴落とすだけでも構いません。まぶたの隙間から目薬が入っていくので大丈夫です。
泣いて嫌がっているときも無理をする必要はありません。泣いているときは、涙で目薬の成分が流れてしまい効果が得られません。そんなときは、よく眠っているタイミングを狙ってみましょう。目頭のあたりにそっとさしておけば、自然と目の中に入っていきます。目の周りについた目薬はティッシュなどで優しく拭き取ります。目薬が皮膚についたままにしておくと、お肌がかぶれてしまうことがあるため注意が必要です。
目薬の容器の先がまつ毛や目やにに触れて汚くならないように気を付けましょう。使用後はしっかりキャップをし、お子さまの手の届かない場所に保管してください。きょうだいで同じような症状でも、目薬の共用は避けましょう。
成長と共に、泣いて嫌がっていたお子さんも上手に目薬がさせるようになります。
目薬がさせたら、たくさん褒めてあげてくださいね。